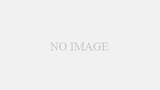断眠によって低下した作業パフォーマンスを自己認知する能力と個人の朝型夜型傾向の関連の検証
要点
- 自分の発揮できるパフォーマンスを自分で認知することをセルフモニタリングと呼びます。
- そこで本研究ではさらにセルフモニタリングに関する知見を得るために、睡眠不足の状況下におけるセルフモニタリングの正確性の変化が、朝型夜型傾向によってどう異なるかを検証しました。
- 結果、朝型傾向が強いほど実験後半(朝)の時間帯でセルフモニタリング成績が有意に低下することが示されました。特に朝のセルフモニタリング能力低下は自身のパフォーマンスを楽観的に見積もる傾向があったため、安全確保の観点でも注意が必要であると考えられます。
内容
現代社会では、多くの労働者が仕事のスケジュールや多すぎる仕事量にによって、睡眠不足状態であることが知られています。
そして、労働者が疲労した時にそのリスクに応じた行動(休憩など)を取るためには、本人が自身のパフォーマンスについて正確にモニタリングする能力(セルフモニタリング)が不可欠です。
そこで本研究では、セルフモニタリングに関する知見をさらに深めるために成人男性26名を対象に実験を実施し、24時間の断眠実験中のセルフモニタリング成績の推移に加えて時間に伴う成績変化と朝型夜型傾向との関連を検証しました。
参加者の朝型夜型傾向(クロノタイプ)はMEQ(Morningness-Eveningness Questionnaire)を用いて評価しました。セルフモニタリング成績は、精神運動ヴィジランス課題(Psychomotor Vigilance Task:PVT)およびDigit Symbol Substitution Task(DSST)において、実際の課題遂行能力と事前及び事後の自己評価を比較することにより算出しました。
結果、PVTとDSSTにおける課題遂行能力と自己モニタリング能力は、深夜4時頃までは維持されていましたが、それ以降は低下しました。そして、特に朝型傾向の参加者では、断眠の最後の4分の1の時間帯では、楽観的なセルフモニタリングが行われやすいという結果でした。なお、この関連が見られたのは事前予測時だけであり、事後予測ではMEQとの関連は見られませんでした。
これらの成果から、職場の管理、特に不規則な勤務時間、交代制シフトや長時間労働のある職場において、より良い労働安全を確保するためには個人のクロノタイプを考慮することが重要であることを示唆しています。
論文情報
| 掲載誌 | Chronobiology International |
| 論文タイトル | Association of self-monitoring performance of cognitive performance with personal diurnal preference when sleep-deprived |
| 著者 | Yuki Nishimura, Michihiro Ohashi, Taisuke Eto, Sayuri Hayashi, Yuki Motomura, Shigekazu Higuchi, Masaya Takahashi |
| DOI | doi://10.1080/07420528.2024.24 |